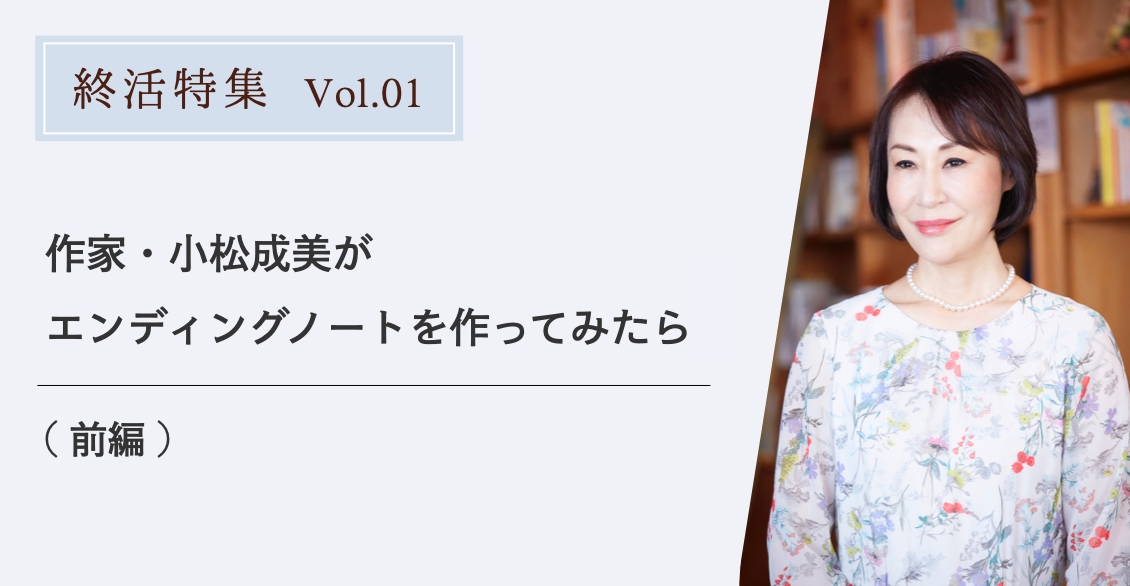健康な今だからこそ始めたいエンディングノート
1990年に本格的な執筆活動を開始し、作家として30年の年月を過ごしてきました。そして、2022年には60歳を迎えます。人生の後半戦を生きる私は、人生について振り返り、最期を迎えるときのことを考えるようになりました。
そこで私が思い立ったのは、「エンディングノートを書き始めよう!」というものでした。エンディングノートとは、人生の最期を迎える前に自分の希望や伝えておきたいことなどを書き残すことを指します。言い換えれば、「終活」「生前整理」ともいえますね。
多くの方々は、「50代でエンディングノートを書くなんて、まだ早いのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。実際、私自身もそう考えていました。70代80代になったら遺言を記せばいい、とぼんやり考えていたのです。しかし今は「何事も、準備は早い方が良い」と感じています。むしろ、気力も体力もあり、現役の作家として仕事に邁進している今だからこそ、しっかりと人生のエンディングに向かうロードマップを記すべきだと考えました。
80代の両親の存在
なぜ、私がエンディングノートを書こうと思いたったのか。まずはその背景からお話しいたしましょう。
エンディングノートを書くきっかけは、一緒に暮らしている80代の両親の存在でした。母は70代のときに、父は80代のときにがんを患いました。適切な医療を受けられたおかげで、ふたりは健康を取り戻すことができ、今ではがんも完治し健やかに暮らしています。
二人ががんになった当時、私は両親の死に向き合いました。両親にしても、自分の死後について語っていました。
ところが、健康を取り戻してからは自分たちの終末を考える気持ちから遠ざかっているように見えます。
父ががんになったときのことです。公的な書類を作成する必要があり、長女である私は、役所や銀行、生命保険会社に行き、代理人になる手続きをしようとしました。しかし、そういった手続きのほとんどは、本人の手続きが必要で、身内であっても代理になることはとても難しかったのです。そのとき、「もし両親が意識不明になったり、認知症になったりしたら大変なことになるな‥…」と、実感しました。
一度は命の危機を味わった両親ですが、おだやかな日常が続くと、むしろ生きることに懸命で終活は休止となりました。父は、以前のように銀行や投資信託の口座など、自分自身で管理しています。元気に過ごしているとはいえ、高齢の両親に「最期に備えてほしい」とはなかなか言えず、どうしたものかと頭を抱えることになりました。
もちろん両親の健在を、私は幸福に思います。100歳になっても健康でいてほしい。そう願うと同時に、この先の不安が拭えないのも事実です。もし、仮に両親が今の私の年齢だったとしたら、「死期」を話題にすることに気まずさはなかったでしょう。あの頃に、将来のことを決めておけば良かったと、繰り返し考えるようになったのでした。
そして、私はふと、自分に置き換えて考えてみたのです。私は独身で、両親が亡くなれば血縁は一つ違いの弟だけです。おそらく自分の終末は、血縁ではない誰かにお願いすることになるでしょう。そのとき、その人たちに大きな負荷をかけたくない、と思うのです。
両親にとっては「親の最期は子どもが看取るもの」という考えがあります。自分で終末のための準備をすることは、もはや簡単にはできないだろうと感じます。それでも、私にできることは精一杯やっていこうと心に決めています。
だからこそ、自分自身は、エネルギーが充実している今のうちに死に向き合い、自分自身の人生を振り返るエンディングノートを書いてみようと思い立ったのです。
執筆作品への想い
エンディングノートを書きたいと思ったのには、もうひとつ理由があります。「作家」という職業に就いて歩んできたからこそ、執筆した作品を整理しておきたい、と思いました。

私は、「創作する」という仕事に、文字通り人生をかけてきました。キャリアのほとんどを、本を書くこと、雑誌や新聞に記事を書くことに費やしてきたのです。人生の時間のほとんどを作家という仕事に費やした自分は、家族を持ち、子育てもする、という人生を選択しませんでした。20代、30代、40代ではキャリアを築くことに全身全霊を傾けましたし、50代で豊かな収穫の時期を迎える実感も得たのです。
そうした日々のなかで、たくさんの作品が生まれました。現在まで50冊ほどです。この先も著作を増やしていくつもりです。
作品こそが、私にとって大きな財産です。世に送り出した作品には、プライドと責任を持っています。作品は後世の方々にも読んでいただきたいですし、主題となってくださった方々、取材を受けてくださった方々には改めて礼節を尽くしたいです。
作品の一つ一つをつくるために力を貸してくれた編集者や出版社の皆さん、取材に協力してくださった方々、そして、私の本を読んでくださる読者の皆さんには本当に感謝しています。だからこそ、そんな皆さんに向けて、自分が元気なうちに作品に込めた想いや時代の背景など、一作ごとに書き残していきたいと思っています。